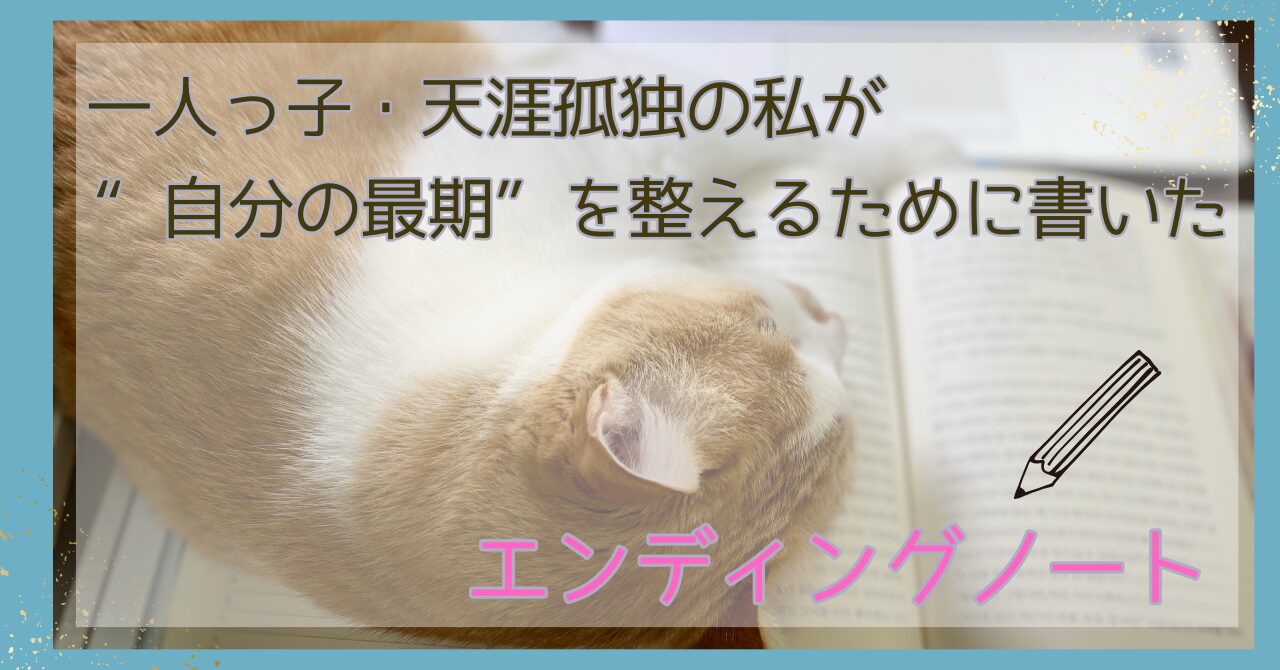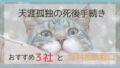「あなたが亡くなったあとのこと、誰がやってくれますか?」
家族がいない、頼れる人もいない。
最後にお世話になるのは間違い無く第三者。

そんなおひとりさまに是非書いてほしいのがエンディングノートです。
「エンディングノートって、家族に向けて書くものじゃないの?」
そう思っている方もいるかもしれません。
誰もが葬儀や相続のことで家族に苦労をかけたくないと考えるからです。
私は母の見送りから葬儀、その後の手続きまで、すべてをひとりでやってきました。
一緒に暮らしていた母のことなのに、彼女の意志を聞いておかなかったことでとても苦労しました。
見ず知らずの第三者ならなおのこと。
死後に関わる“第三者”の手を煩わせないために伝えるべきことをしっかり残しておくことが必要だと思っています。
- そろそろ終活を始めようかと考えている方
- 自分の最後を任せる家族がいない方
“天涯孤独”の私がなぜエンディングノートを書こうと思ったのか。
その理由と必要性を、経験を交えてお伝えします。
天涯孤独の人にとってのエンディングノートの意味

見せるノートではなく情報を伝えるためのノート
「書くことがない」
はじめてエンディングノートを開いたとき、私が真っ先に思ったことです。
多くのエンディングノートは、家族が読むことを前提に作られています。
たとえば
- 自分の生い立ちや人生の振り返り
- 家族や友人へのメッセージ
- 子どもの名前の由来や思い出話
といった“気持ち”を残す項目が並んでいます。
でも私は天涯孤独。
そんな私がそれを書いたところで、読んでくれる家族はいません。
むしろ知らない人にそんな個人的な思いを見られるのは少し抵抗すらありました。
「書きたくない」
「書くことがない」
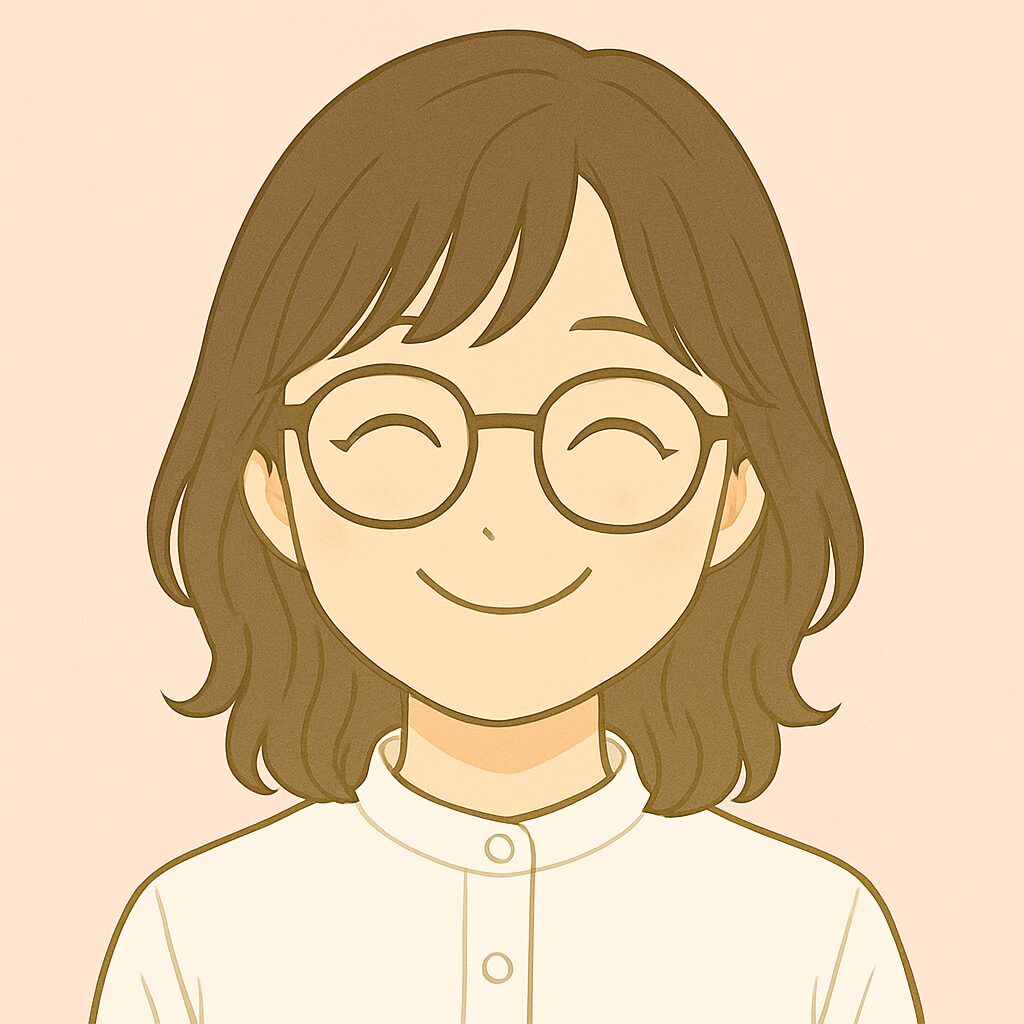
それなら無理に書く必要なんてないと思ったんです
思い出の欄は空欄でもまったく問題ありません。
私にとってのエンディングノートは「誰かに見せるもの」ではなく「情報を伝えるためのノート」でいいのです。
自分の最後に関わってくれる“誰か”が必要な手続きをスムーズに進められれば十分です。
だから私は気持ちの部分はスッと飛ばして、事務的に必要な情報だけを記すようにしています。
それが天涯孤独の自分にとっての“ちょうどいいエンディングノート”の使い方なのだと思っています。
なぜ普通のノートではなくエンディングノートなのか
「事務手続きのためだけなら、普通のノートでもいいんじゃない?」
そんな声が聞こえてきそうです。
確かに必要な情報だけをまとめるだけなら、シンプルなノートで十分かもしれません。
でも私があえてエンディングノートを選んだのには理由があります。
それは「抜け漏れを防げるから」です。
人は自分の人生の終わりについて、体系的には考えられないものです。
これで大丈夫と思って書き終えたつもりでも
「あれを書き忘れた」
「これはどうするんだっけ?」
と気づくことがあるのです。
エンディングノートには、そうした“気づき”のきっかけとなる項目が、あらかじめ用意されています。

葬儀、保険、財産、希望する最期の迎え方など、終活にまつわることが網羅的に並んでいるので書いておくべきことを忘れることがありません。
もちろん、すべての項目を埋めなくても大丈夫。
必要ないと思えば飛ばして構いません。
必要なことを見落とさずに書いておけるという点で、エンディングノートはとても頼もしい存在です。
終活に慣れていない人ほど、最初の一冊にはエンディングノートをおすすめします。
今を生きるヒントになる
エンディングノートの一番の目的は、亡くなったあとの事務手続きをスムーズに進めてもらうためです。
でもそれだけではありません。
エンディングノートには、もうひとつ大きな意味があります。

それは「自分の人生の最後をどう迎えたいか」を自分に問いかけることで、今の生き方にもヒントを与えてくれることです
普段私たちは自分の葬儀や介護のことなど、なかなか考える機会がありません。
もし重い病気になって、余命を宣告されたらと想像するだけでも心が重くなります。
エンディングノートの質問に答えていくことは、自分の本音と向き合う大事なきっかけになります。
避けてきた問いに向き合い、どうしたいのかを自分の言葉で書く。
そうすることで“自分はどんな最期を望んでいるのか”が見えてきます。
そして不思議なことに“終わり”が見えてくると、“今”をどう生きるかも自然と見えてくるのです。
エンディングノートは未来の誰かのためだけでなく、今を生きるヒントになるのです。
いつ書けば良いのか
エンディングノートは、いつから書き始めても大丈夫です。
「まだ若いから」
「まだ元気だから」
と思うかもしれませんが、実は早いうちから始めるのが理想です。
人生はいつ何が起こるか分かりません。
もしもの時に備えて、少しずつでも書き始めておくと安心です。
書き始めたばかりの頃はまったく、まったくペンが進まないかもしれません。
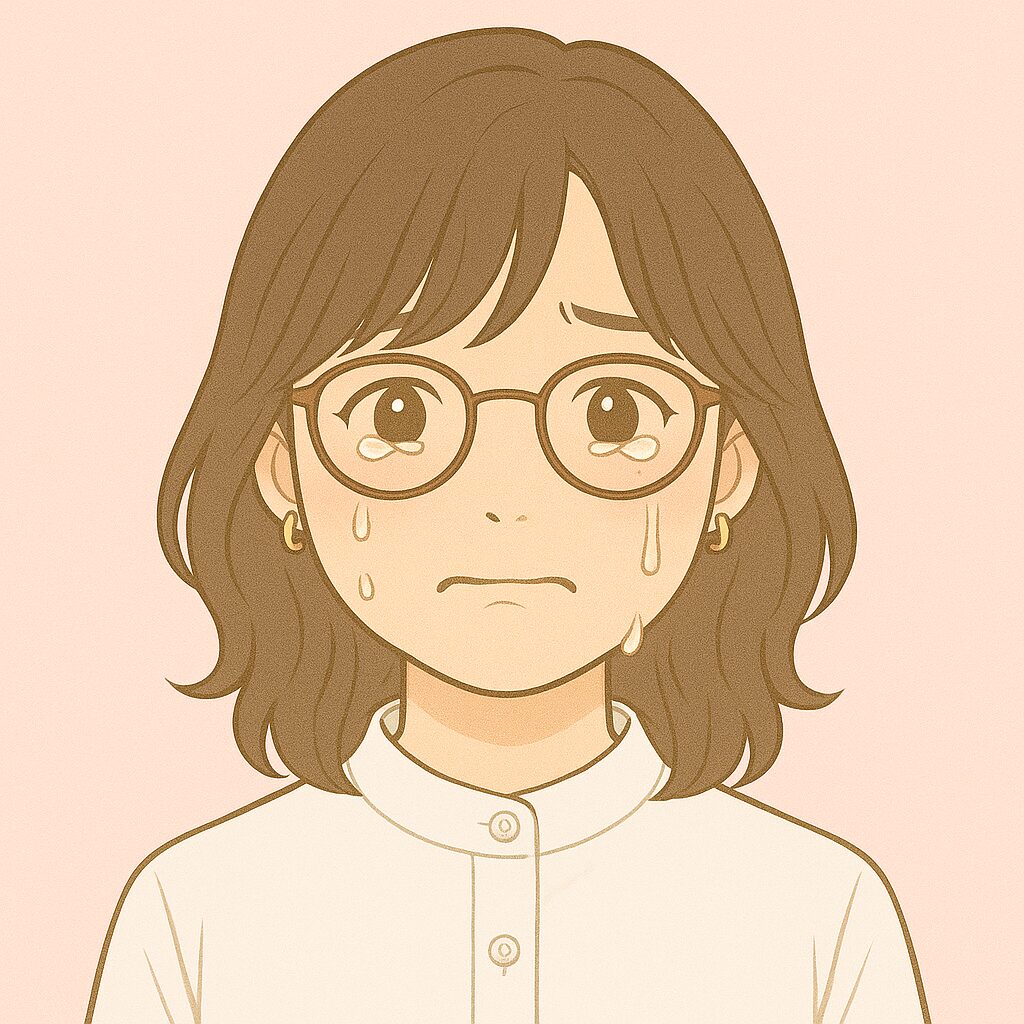
私も1時間以上も眺めた結果、何も書けずにノートを閉じたことがありました
「書けるところから」
「気になったところだけ」
軽い気持ちで始めてみてください。
最初は空欄があって当たり前だし、それで良いのです。
私が実践しているのは鉛筆で書くこと。
時間が経てば自分の気持ちや生活環境は目まぐるしく変わっていきます。
鉛筆なら何度でも書き直しができます。
そのときどきの「今の自分」に正直に書いていけば、それがいちばん意味のあるノートになります。
エンディングノートは「終わりの準備」だけではなく「今を見つめるツール」でもあります。
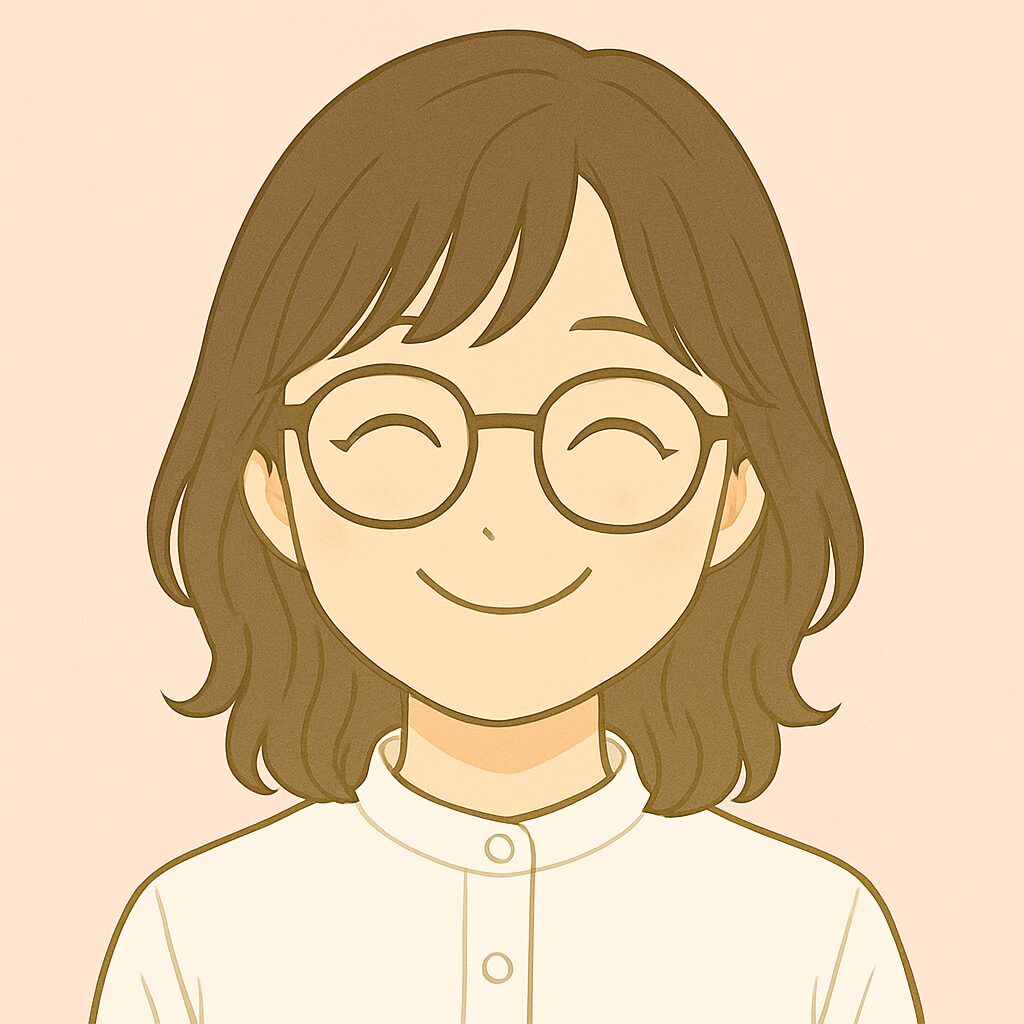
早く始めて、ゆっくり続けていきましょう
エンディングノートに書いておくべきこと
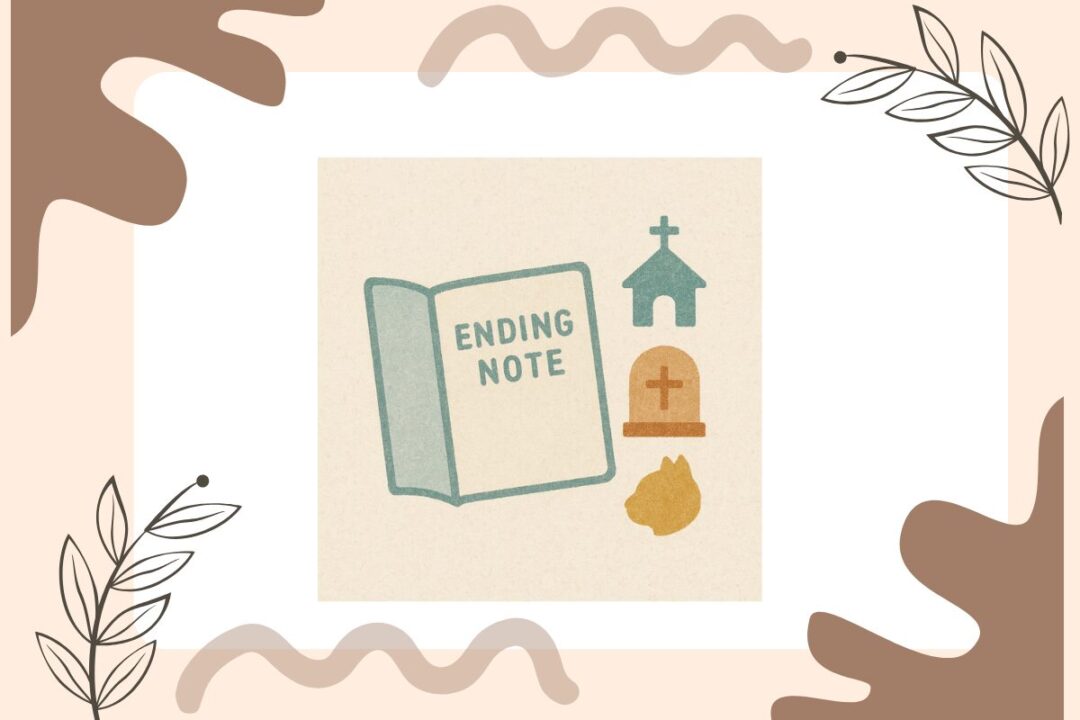
基本情報
基本情報として最低限書いておくと良いことは以下のとおりです。
- 名前
- 生年月日
- 住所
- 本籍
- 筆頭者の名前
「本籍」と「筆頭者」は日常生活であまり使うことがありませんよね。
これらは戸籍謄本の取り寄せに必要な項目です。
年金や相続の手続きは戸籍謄本がなければ進めることができません。
「本籍」と「筆頭者」がわからない場合、第三者があなたの代わりに取得するとなると一定の条件を満たす必要があります。

自分自身であれば住民票で簡単に確認できますよ
届出や解約が必要なもの
亡くなったあとの手続きで、家族や第三者がもっとも苦労するのが「契約の解約」です。
どんなサービスや契約をしていたかがわからないと、対応に時間も手間もかかってしまいます。
契約には「請求しないと支払ってもらえないもの」と「解約しない限りずっと請求が続くもの」があります。
請求しないと支払ってもらえないもの
- 銀行口座
- 証券口座
- 年金
- 生命保険や医療保険など
これらは、申請しないと自動的には支払われません。
手続きを任される人が知らなければ、受け取るべきお金を受け取れない可能性もあります。
解約しない限りずっと契約や請求が続くもの
- クレジットカード(年会費)
- 固定電話・携帯電話
- 電気・ガス・水道
- インターネットのプロバイダー契約
- サブスク(動画配信や音楽サービスなど)
- ジムや各種会員制サービス
こうした契約は自分が思っている以上に数が多いものです。
エンディングノートに書ききれないかもしれません。
少しずつ見直して、できれば不要な契約は整理しておくことも大切です。
私は一覧表を別に作って、エンディングノートに添付しています

契約社名と一緒に解約時の連絡先も書いて、定期的に見直しています
注意点としてクレジットカードやキャッシュカードの暗証番号は絶対に残さないこと。
悪用される恐れのある情報は記載しないようにしましょう。
終末期医療についての希望
自分の最期が近づいたとき、どこまでの医療を望むか。
これは元気なうちにしか決められない大切なテーマです。
たとえば以下のような希望があります
- 延命治療を望むのか
- 緩和ケアを優先したいのか
- 意識がなくなった場合、どこまで医療行為をしてほしいのか
こうした判断は、いざという時に自分では伝えられないことが多いもの。
だからこそ事前にノートに書いておくことが大切です。
もちろん実際の医療行為には医師の判断や法律の制約があります。
書いた通りに実現できない可能性だってあるでしょう。
でも「本人がどうしたかったのか」が明確に残っているだけで周囲の迷いや後悔を減らす助けになります。
エンディングノートは、誰かに判断を委ねるときの“道しるべ”。

自分の意思を尊重してもらうために、しっかり言葉にして残しておきましょう
葬儀の方針
葬儀をどのようにしてほしかったのか。
これは残された人がもっとも悩むことかもしれません。
たとえば以下のような内容を、あらかじめ決めておきましょう。
- 葬儀を行うか、行わないか
- 形式はどうするか(直葬、家族葬、一日葬など)
- 費用はどこから出すのか(預金、保険など)
自分の希望をはっきり残しておけば悩まずにすみます。
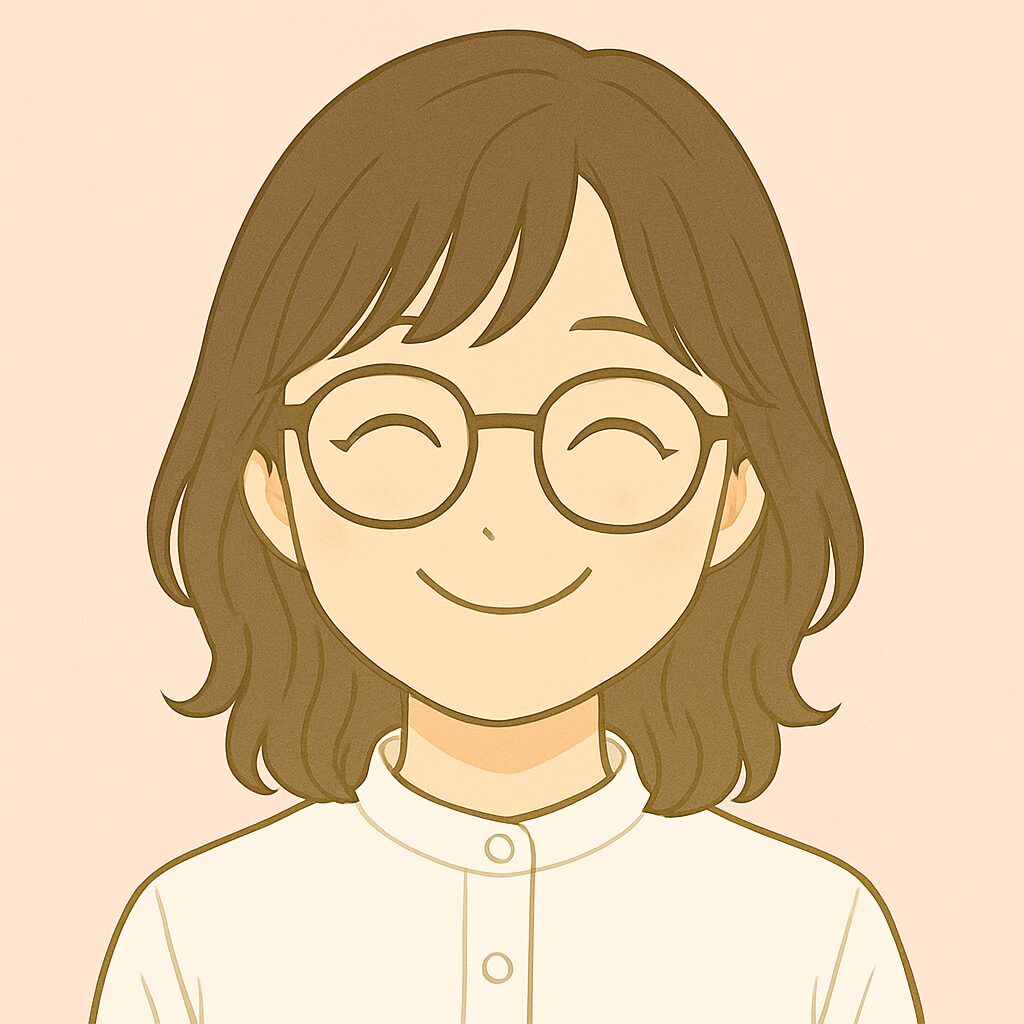
特別なこだわりがなければ「最低限でいい」など、ざっくりとした希望だけでも書いておきましょう
連絡してほしい人
万が一のときに連絡してほしい人がいれば、その情報も書いておきましょう。
氏名・連絡先、そしてその方との関係を明記しておきます。
- 勤務先の上司・同僚
- 賃貸住宅の大家さんや管理会社
- 親しい友人や長年連絡を取り合っている知人
- ペットの世話を頼んでいる人や動物病院
- 遺品整理や死後事務を依頼する専門業者
ペットの託し先について
ペットを飼っている方は、自分に万が一のことが起きた時にどうするかも課題です。
天涯孤独にとってペットは家族。
その子にとっての最善策を決めておく必要があります。
本当に信頼できる知人であれば事前にお願いしても良いかもしれません。
でも第三者にお願いするのは心配な方もいるでしょう。
動物を飼うにはお金もかかるし、その人が最後まで気持ちが変わらないという保証がないからです。
そんな時の選択肢として「ペット信託」という制度があります。

費用や手間はかかりますが「うちの子をちゃんと守ってもらえる」という安心感は何にも代えがたいものです。
命を預かるということは、どんな形であれ最後まで寄り添う覚悟を伴うものです。
将来の不安がある方は、ペット信託を一つの選択肢として検討してみることをおすすめします。
家の後始末について
繰り返しになりますが、人は自分が思っている以上に沢山の物の中で暮らしています。
その量が多ければ多いほど、金銭面でも体力面でも片付ける人の負担が大きくなります。
まずは物を減らすことから始めましょう。
そのうえで生前のうちに見積もりを取り、信頼できる遺品整理業者を見つけておくと安心です。
財産の寄付先について
預金や不動産などの財産がある方は、残された財産の引継ぎ先を決めておく必要があります。

わずかでも財産が残せるなら、動物保護団体へ寄付したいと思っています
実はエンディングノートに「財産の寄付先」を記載していても、それだけでは法的効力はありません。
正式に財産を誰かに譲りたい、あるいは団体などに寄付したい場合には、公正証書遺言など法的に有効な遺言書の作成が必要になります。
遺言書がない場合、財産は最終的に国の物になります。
又、遺言書があっても不備があると無効になってしまう可能性だってあります。
遺言書は弁護士等の専門家に相談して作成することを強くおすすめします。
今後進めていく予定の私の終活
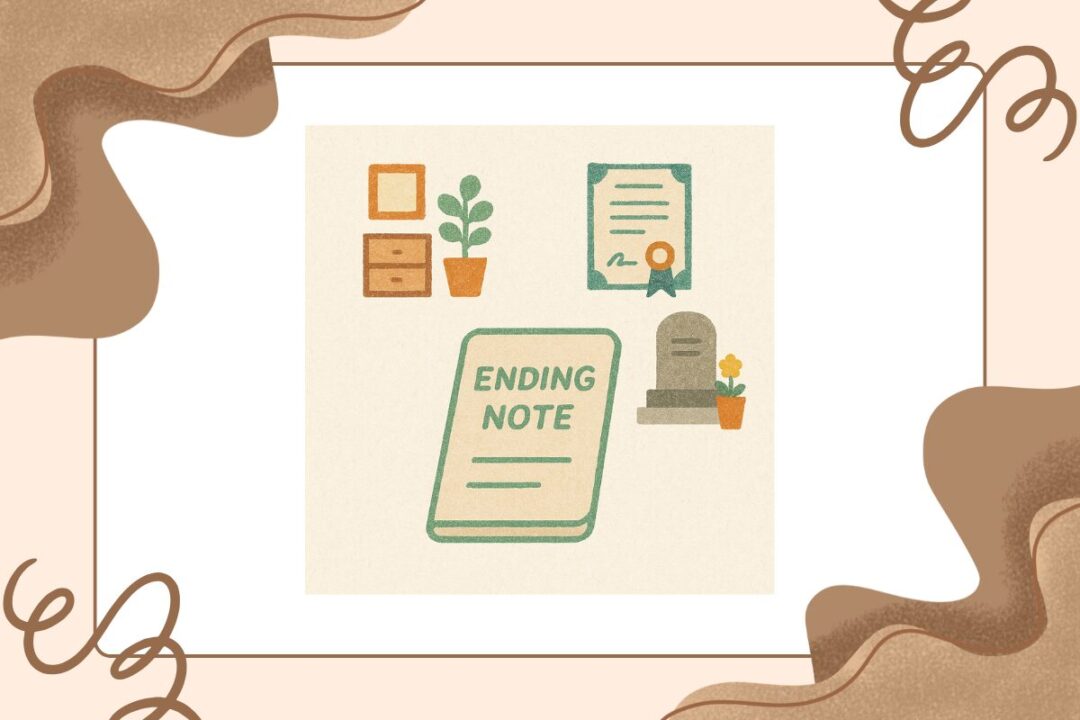
もたない暮らし
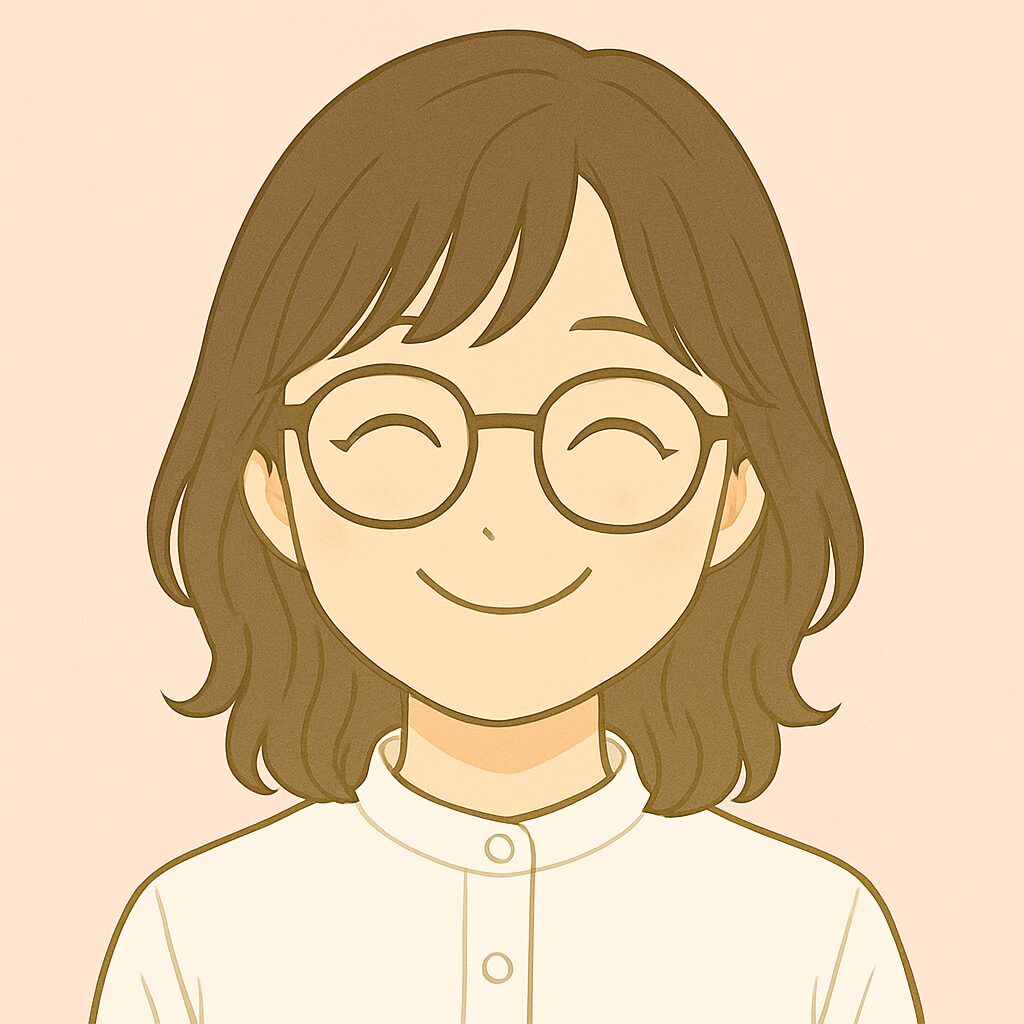
母の遺品整理を経験して「物を片付ける」という作業がいかに大変かを身をもって知ったからこそ、なるべく物を持たず小さく暮らすことを意識しています
服も日用品も、たくさんは必要ありません。
お気に入りの物だけを厳選して持つことで、気分もすっきり整い、日々の暮らしが心地よくなりました。
これからの人生。
自分らしく過ごしていくために「もたない暮らし」は終活の大切な一歩だと感じています。
関連記事
天涯孤独の50代女性へ|服を減らすことが未来の自分をラクにする理由と増やさないための3つのルール
死後事務委任契約
死後の手続きについては弁護士と「死後事務委任契約」を結ぶ予定です。

それなりの費用はかかりますが第三者に気を使うこともなく、ビジネスライクに責任を持って対応してくれるなら高すぎる費用だとは思っていません。
今後入院することを想定して、身元保証サービスもあわせて契約するつもりです。
私が検討している身元保証サービスはこちらで詳しくご紹介しています。
天涯孤独の不安解消!「終活と相続のまどぐち」無料相談体験レポート
墓じまい
私にはお墓を継承してくれる子どもがいません。
それは私が死んだら祖母と母が眠るお墓の管理ができなくなることを意味します。
いつかは墓じまいをしなくてはいけないなと考えていました。
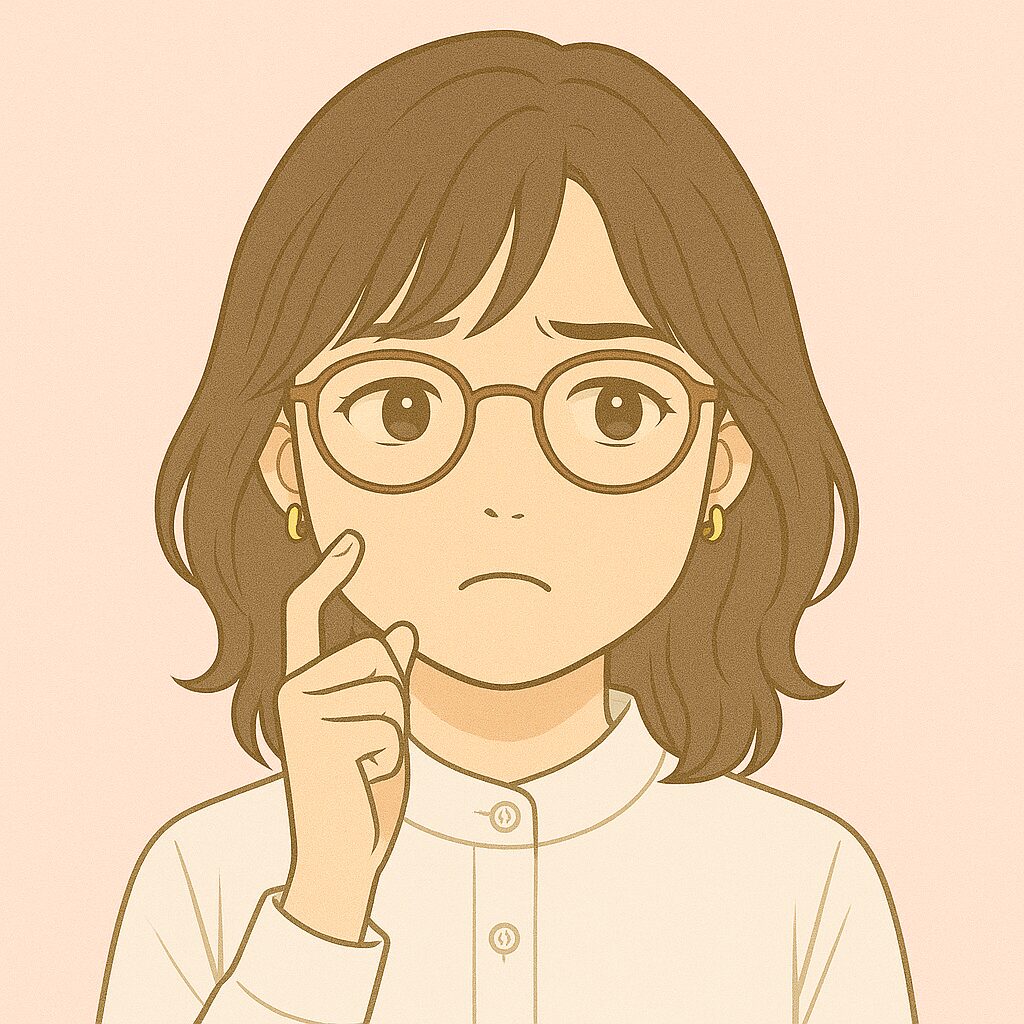
お墓の香炉や花立てを持ち上げての拭き掃除も年々辛くなってきています
そんな時、同じ市営墓園内に合葬墓地ができることになりました。
私と同じように墓の承継問題に悩む方が多いのでしょう。
年に一度、希望者を募る案内が届きました。
合葬墓地には既に埋葬されている遺骨だけでなく、生前申込みもできるとのこと。
つまり私自身もそこへ入れるということです。
そのためには前もって準備しなければならないことがありました。
合葬墓地に私を納めるための手続きを誰が行うのか、生前のうちに決めておかなければならないのです。
死後事務委任契約を先に進める必要があることがわかり、終活に本腰を入れるきっかけになりました。
定年を迎える前に、まとまったお金がかかることをは済ませておこうと思ったからです。
今年中には正式に死後事務委任契約をして、来年には墓じまいをするのが目標です。
なお誤解されがちですが、合葬墓に納めることは「無縁仏になる」という意味ではありません。
無縁仏とは供養する人がいなくなり、管理されずに放置されたお墓や遺骨が、行政や寺院などにより整理される状態を指します。

私の場合は自分の意思で契約し、信頼できる方に手続きを託すのですから、たとえ合葬墓地でも、私は“縁ある仏”として見送られると考えています。
保管場所
せっかくエンディングノートを準備しても見つけてもらえなければ意味がありません。
かといって、すぐに見えるところに置くのはセキュリティ面が心配です。
調べてみるとエンディングノートを冷蔵庫に保管するという面白いアイデアをみつけました。
これは私の死後の処理をする人が、食べ物が残っていないか確認するために必ず冷蔵庫を開けるから。
茶封筒ごとジップ付きの袋に入れておけば紙の劣化も防げます。
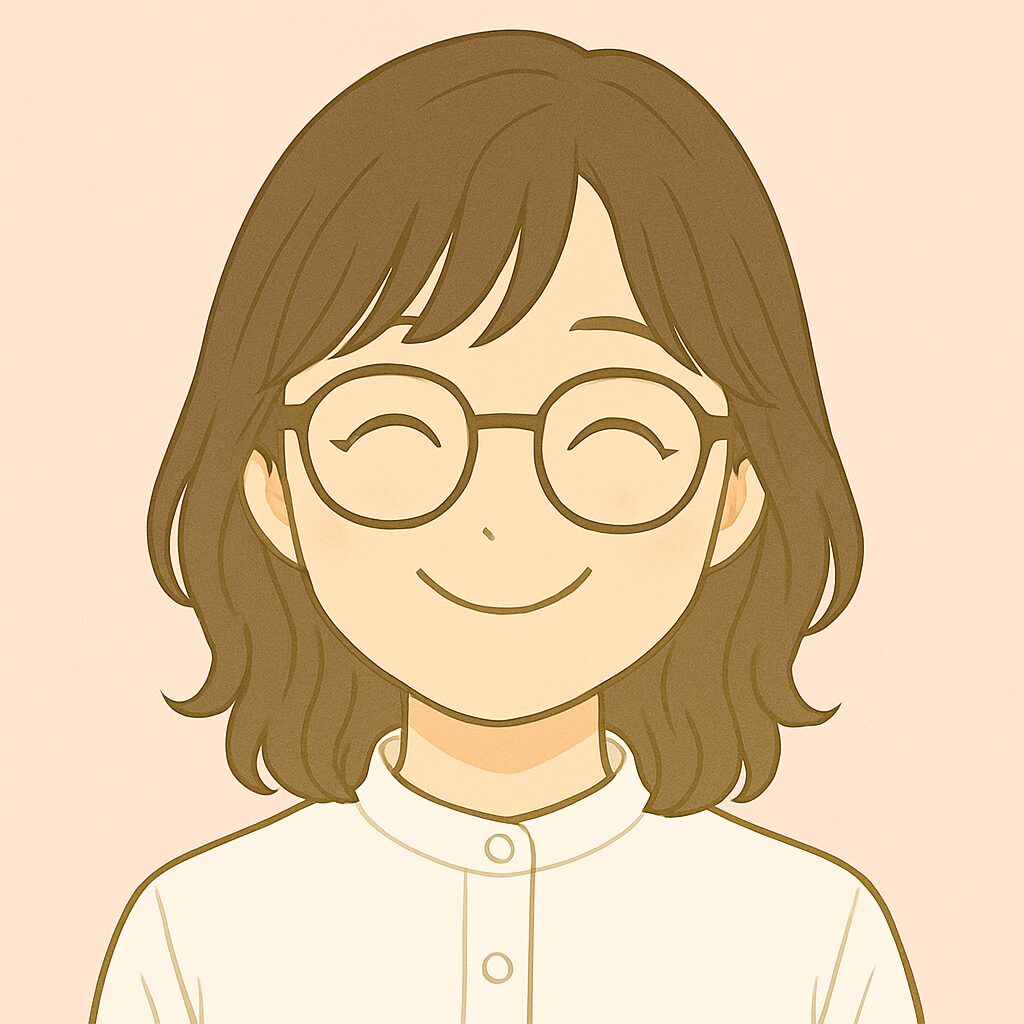
エンディングノートと一緒に自宅の「登記事項証明書」、お墓の権利証、直近の固定資産税の納税通知書を野菜室の手前側に保管しています
目につく場所にあるので変更があった時の修正や追加も面倒ではありません。
まとめ:エンディングノートは今と未来を自分らしく生きるためのノート
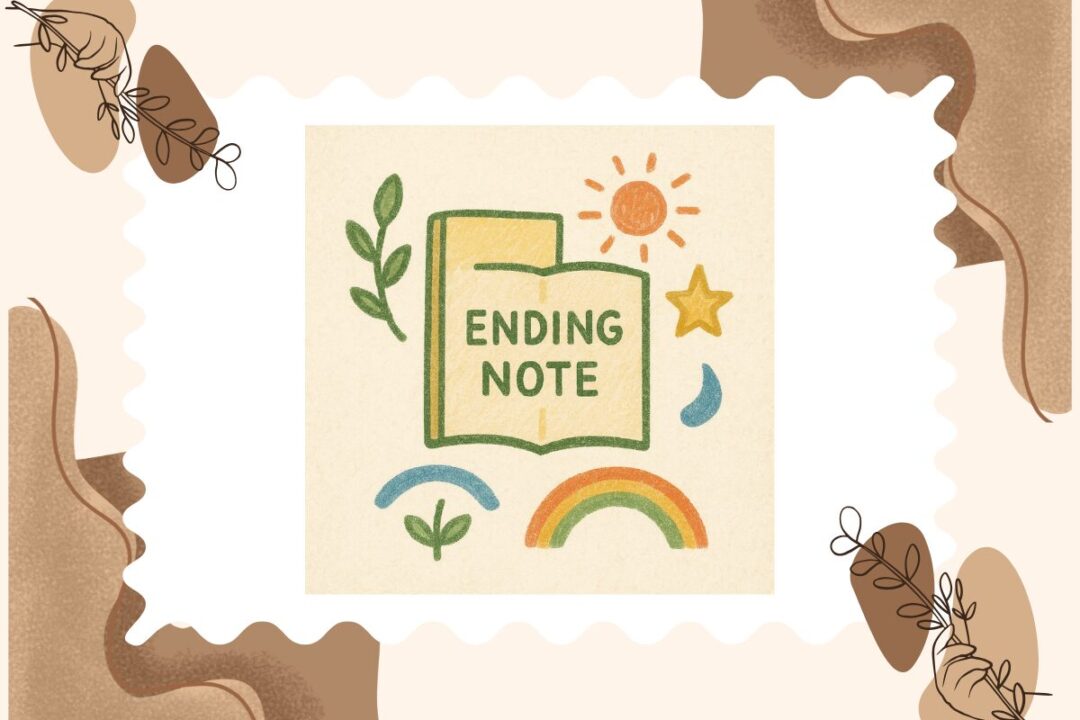
エンディングノートは「死への備え」というよりも「これからを自分らしく生きる」ためのツールです。
年齢や状況にかかわらず、誰にとっても意味があるものです。
- 必要な情報を残すことで、第三者の負担を軽減できる
- 自分の希望や思いを“見える化”できる
- 書くことで気持ちの整理ができ、人生の優先順位が見えてくる
- 基本情報
- 届や解約が必要なもの
- 終末医療や介護についての希望
- 葬儀の方針
- 連絡してほしい人
ペットは家族も同然です。
自分に万が一のことあったときの対策を事前にしっかり考えておくことが大切です。
頼れる人がいない場合の選択肢として「ペット信託」の活用も検討してみましょう。
預金や不動産など財産があれば引き継ぎ先を決めておきましょう。
信頼できる団体への寄付も選択肢の一つです。
エンディングノートに書くだけでは法的効力はありません。
財産を正式に譲りたい・寄付したい場合は、公正証書遺言など法的に有効な遺言書の作成が必要です。
遺言書に不備があると無効になるリスクがあります。
弁護士などの専門家に相談して作成するのをおすすめします。
エンディングノートは何歳からでも始めていい自分のためのノートです。
人生は予想できないことの連続。
だからこそ、心も体も健康な今こそが書き始めるのに最適なタイミングかもしれません。
頼る人がいない天涯孤独の方にとっては「大切な道具」であるとも言えます。
人生が続く限り思いや考えも変わっていくもの。
何度でも書き直していいし、更新してもいい。
自分の思いをしっかり残しておきましょう。

人生の終わりに慌てないために「未来の自分のトリセツ」を作っておきませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。